私が培ってきた哲学を否定できる人とも、一緒に仕事をしてみたい
情報誌『ぴあ』を1日中見ていて、人事部に悪い意味で目を付けられた20代

学校を卒業した後、私はソフトハウスで仕事をし、その会社の常駐先のひとつがぴあでした。ちょうど出版業界はアナログの組版からDTPへの移行期で、私は情報入力のツールやデータベースの開発を担当しました。
当時の私はエンジニアとしてコンピュータばかりいじっていたこともあり出版物にはまったく興味がなく、ぴあのことも知りませんでした。とにかくプログラムを創造、設計、実装するのが好きな、根っからのエンジニアだったのです。休憩時間はいつも情報誌『ぴあ』に目を通していましたが、『ぴあ』を読むのはエンタメ情報収集ではなく「どういうロジックで改行をさせたら読みやすくなるだろうか……」と、システムの改善点を探すため。ところが社内で時間さえあれば『ぴあ』を見ているので、人事部では「いつもぴあばっかり読んでいる人間がいる」と話に上ったほどです。
その後、縁があってぴあ株式会社に入社しシステム部門に配属。しばらくするとMOOK『ぴあmap』をデータベース化してお客様に提供するプロジェクトが動き出し、私はそのチームに配属されました。実は『ぴあmap』にもまったく興味がなく、自分で利用したことはありませんでした。でも今まで世の中になかったものを生み出すことに魅力を感じたのを覚えています。
ぴあは多くのチャレンジを重ねながら成長した
地図は、それを専門にしている出版社や情報会社があります。彼らの多くが全国の情報を持っているのに対し、ぴあは都市部の地図しかもっていません。その中でどうすればお客様が魅力を感じて利用してもらえるか。さまざまなことを考え、エンタテインメントと地図が結び付いた出版物としての『ぴあmap』を、インタラクティブに位置や縮尺はもちろん、ランドマークや掲載コンテンツなどを切り替えられるmapとして、インターネット上にローンチしました。
残念ですが、このプロジェクトは成功したとは言えません。でもぴあは多くのチャレンジを繰り返しながら失敗も経験しつつ成長してきました。現在でもさまざまなことにチャレンジできる環境があります。エンジニア目線で見ると、コストとスケジュール、品質、そしてプロジェクトのゴールさえ守れば、自由に仕事ができる風土があります。
ゴールに辿り着くためにどういう技術を採用するかなどは、エンジニアの裁量に委ねられます。プロジェクトの仲間を信頼し、自由にやらせてもらえるのはエンジニア冥利に尽きると思います。

“趣味的嗜好”の視点がないとぴあのエンジニアは務まらない
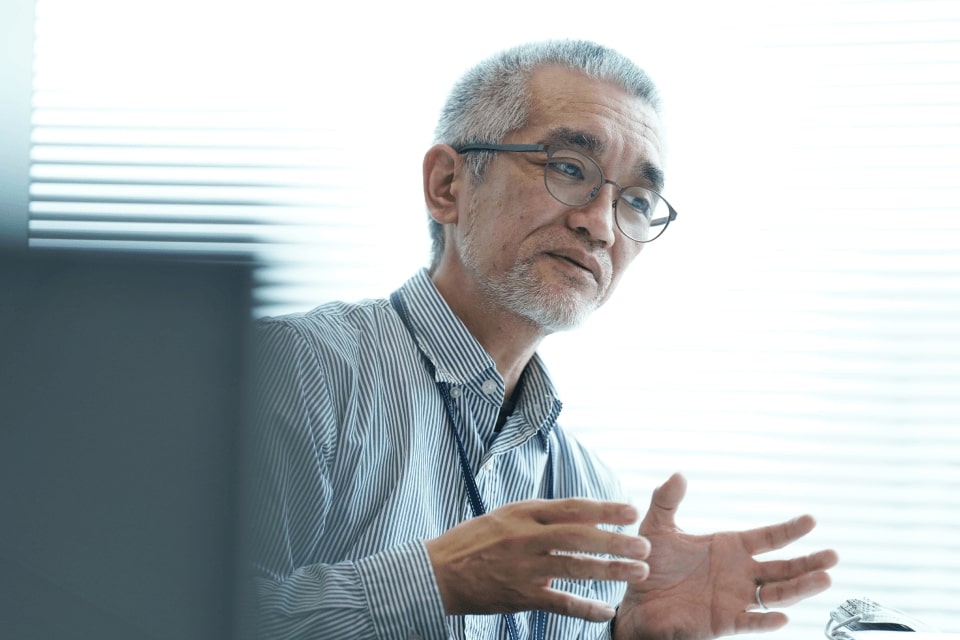
エンタテインメントにおけるチケッティングのあり方は時代とともに大きく変わりました。かつてはお客様が店頭や電話でチケットを買い、紙のチケットを発行。そして会場でスタッフがチケットの半券を切り取って入場しました。現在ではウェブサイトで購入し、電子チケットで入場する公演も珍しくありません。
ぴあのビジネスは『エンタテインメントのインフラ』として『感動のライフライン』を実現することに根ざしています。私は“インフラ”、“ライフライン”を作るんだという意識しか持たないのはぴあのエンジニアとして不十分だと思っています。
大好きなアーティストのライブに行く。お客様はそう考えただけでワクワクしますよね。つまりチケットを手に入れるところからエンタテインメントは始まっているのです。ぴあのエンジニアには“機能”と“趣味的嗜好”、両方の視点が必要です。インフラとして、手に入れたチケットが確実に発行されてきちんと入場できることと同時に、どうすればチケットを手に入れるところからエンタテインメントの楽しさや面白さを感じてもらえるか。サービスのあるべき姿を追い求め、現実解を考えながら、システム構築していくのが、ぴあのエンジニアに求められる力だと考えます。
ただしそのバランスに正解はなく、サービス特性の上で、常に揺れ動いてきました。今後も変わっていくでしょう。時代によって何が求められているかを感じ取りながら、新しいことにチャレンジする。これもぴあのエンジニアならではの醍醐味ですし、世の中の流れを感じ取れる人が大勢いると、面白い職場になるでしょうね。
普通なら絶対に接点が生まれない人とも一緒に仕事ができる
これまでエンタテインメントについてお話しましたが、実は私はいわゆるエンタテインメントにあまり興味がないのですよ。これまでの人生でコンサートにはプライベートでは1度しか行ったことがありません。とはいえ、仕事を通じて、エンタテインメントに興味を持っている人とたくさん触れて、感じ方、考え方などが身に沁みついています。
また、エンタテインメントを軸にさまざまな職業の方と関わるのも、この会社ならではだと思います。私も出版物に関わっていた時は出版業界の方、『ぴあmap』に携わっていた時は地図業界の方と一緒に仕事をしました。普通にエンジニアとして仕事をしていたら絶対に接点が生まれない方たちと関われるのは刺激的ですし、自分の成長につながることを実感できます。

ツボさえ外さなければあとは自由にできる。そんな環境を創りたい

システム開発は事業主体と開発会社という“受発注の関係”で仕事を進めることが多いと思います。そうするとどうしても関わる人が限られてきます。たとえば私の立場だと、実際にコーディングをされている方と話をする機会は滅多にありません。
今回システム部門を内製化するにあたり、必然的に工程によらず開発に関わる方々がぴあのサービスやビジネスに寄り添う環境が生まれます。だからこそ、メンバー同士が同じ目標に向かい、身近な人同士として話し合っていけるような組織を創りたいと考えています。
一方で、仕事の進め方については「好きにすればいい」と思います。もちろん社会人なので一定の制約はありますが、それさえ守ればあとは自由な発想で仕事をしてもらいたいですし、失敗を恐れる必要はありません。一つ付け加えるなら、お客様が熱量を持ってぴあに触れてくる部分がどこか、そこに何が必要かだけは絶対に外さないこと。それだけは忘れないでほしいですね。
これまで私はエンジニアとしてさまざまな仕事をしてきました。その意味で私には私なりの“仕事に対する哲学”があります。人が成長するためには誰かを目標にして、その人を真似ることも大切です。若い人には私を真似てほしいと思うところもありますが、一方で最終的には自分らしさを大事にしてほしいとも感じています。その意味で、私のやり方やマインドを否定してくれる人にもぴあでチャレンジしてもらえると面白いでしょうね。
もちろん、私は新しく入ってきてくれた人に負けるつもりはありません。世間にはSEの寿命は30代後半までという人もいますが、私は一生プログラマーであり続けるつもりでいますから。
